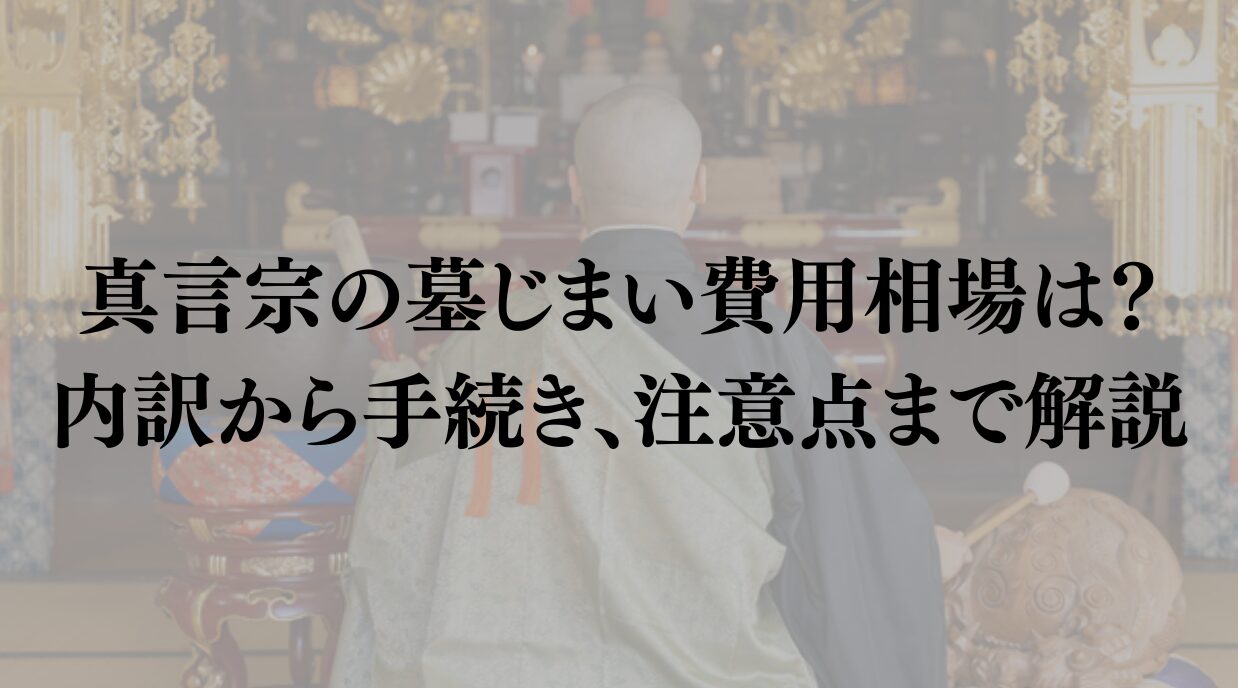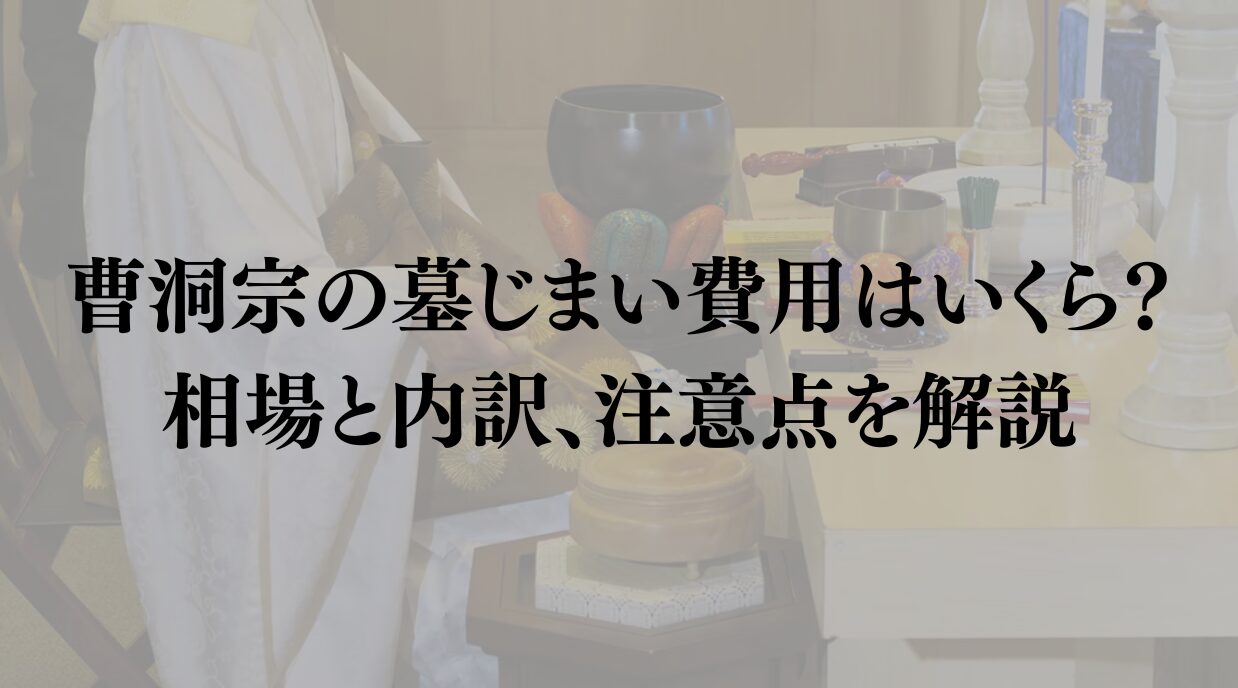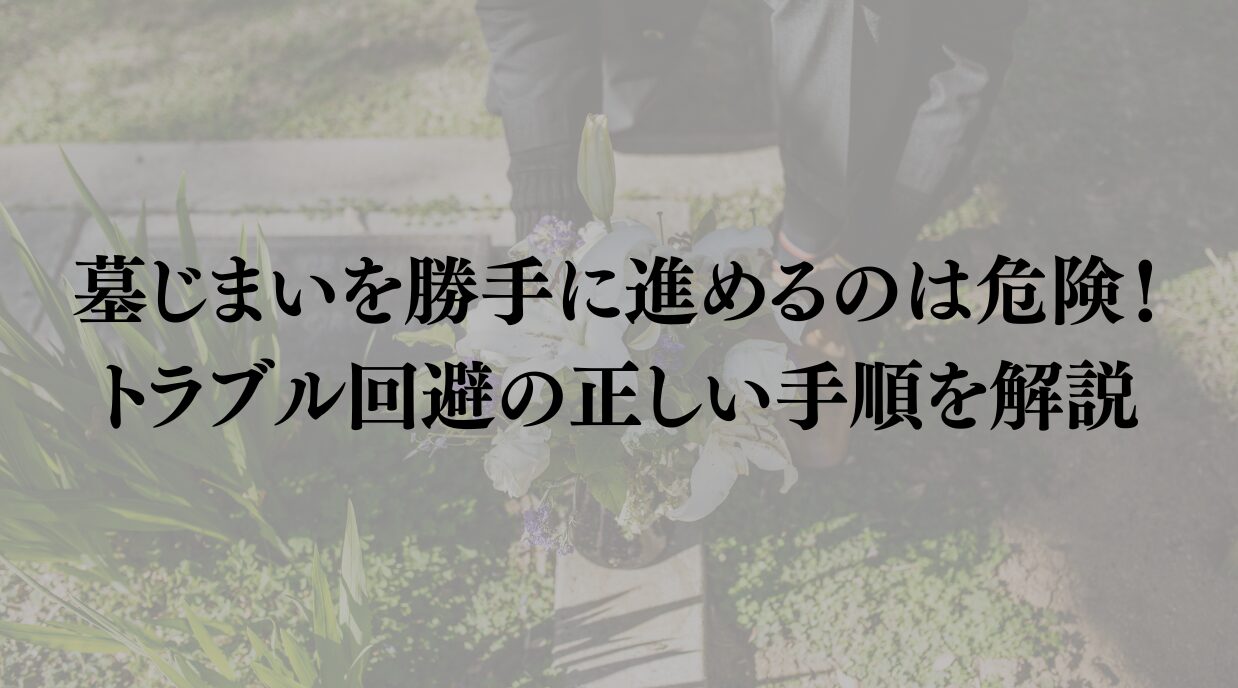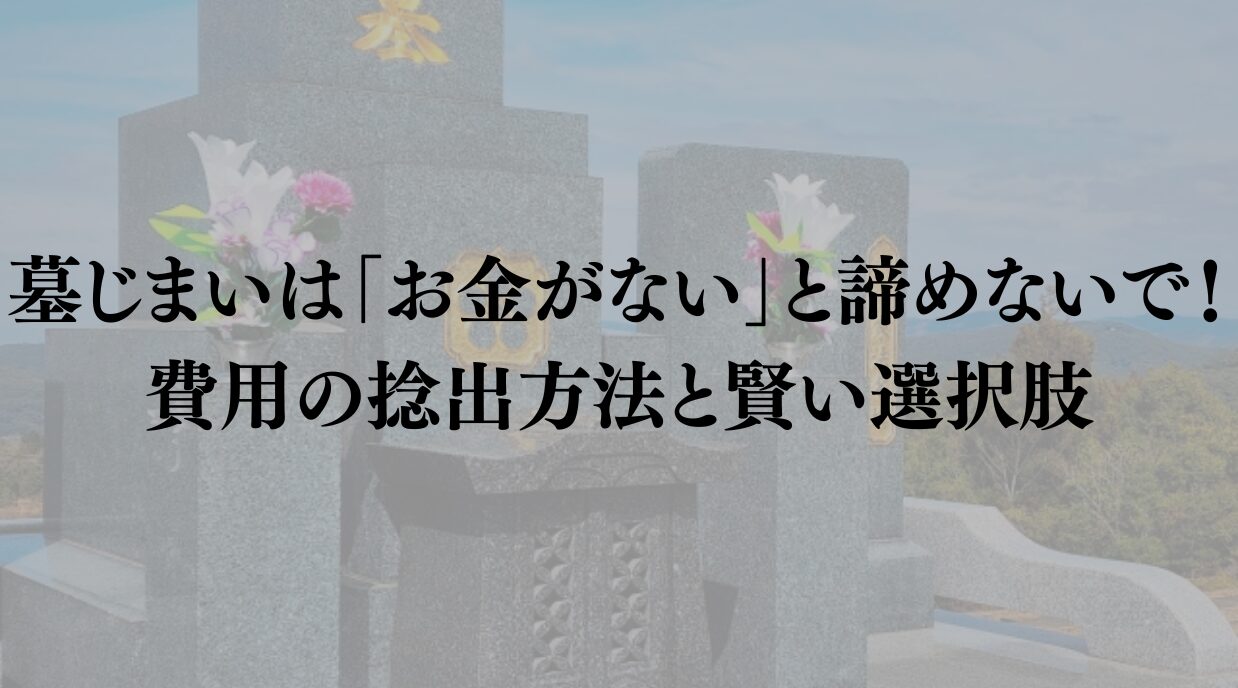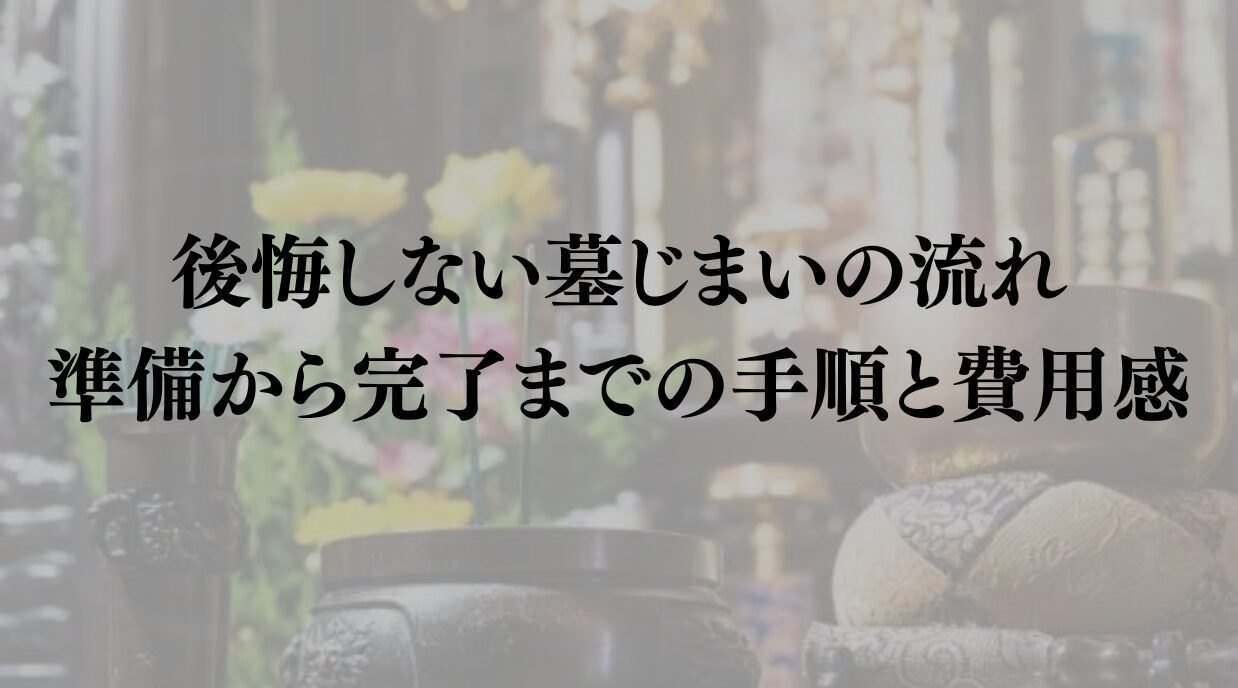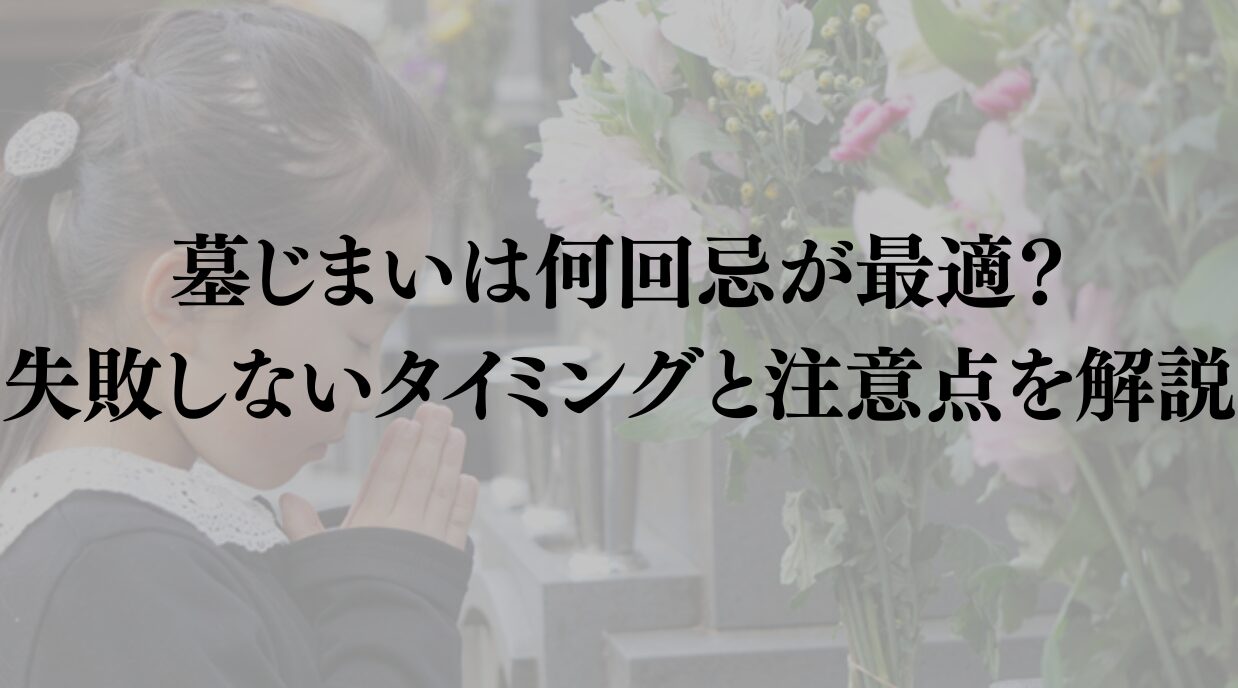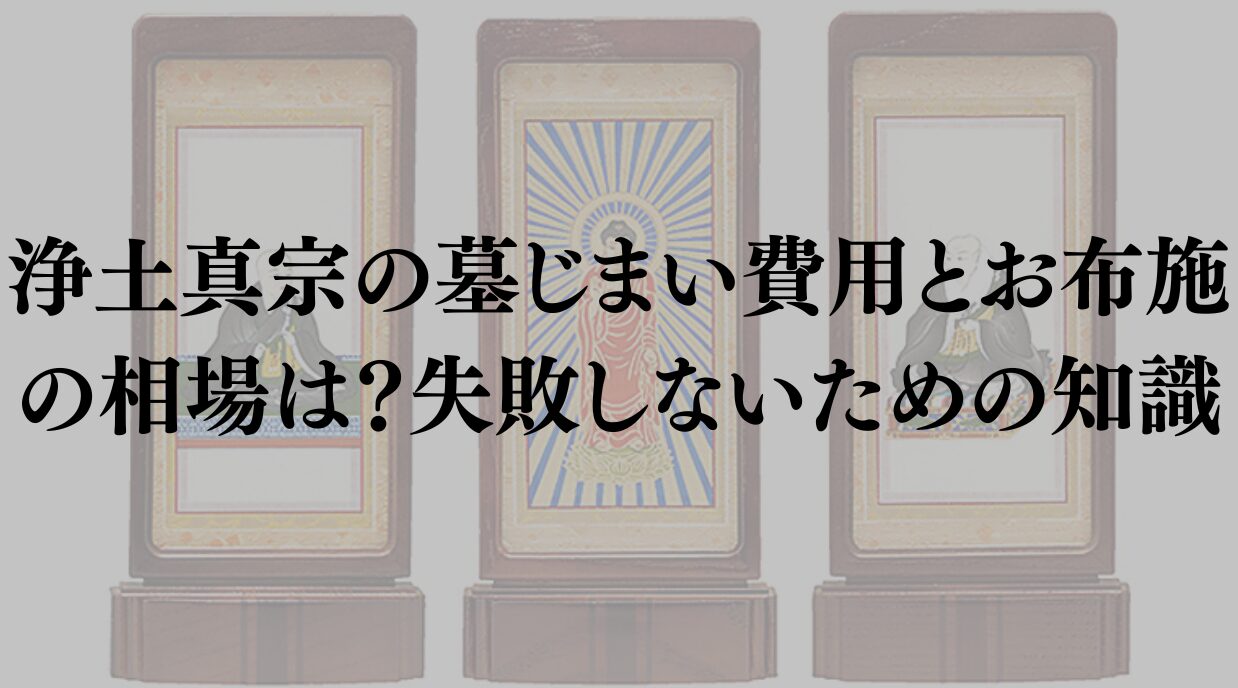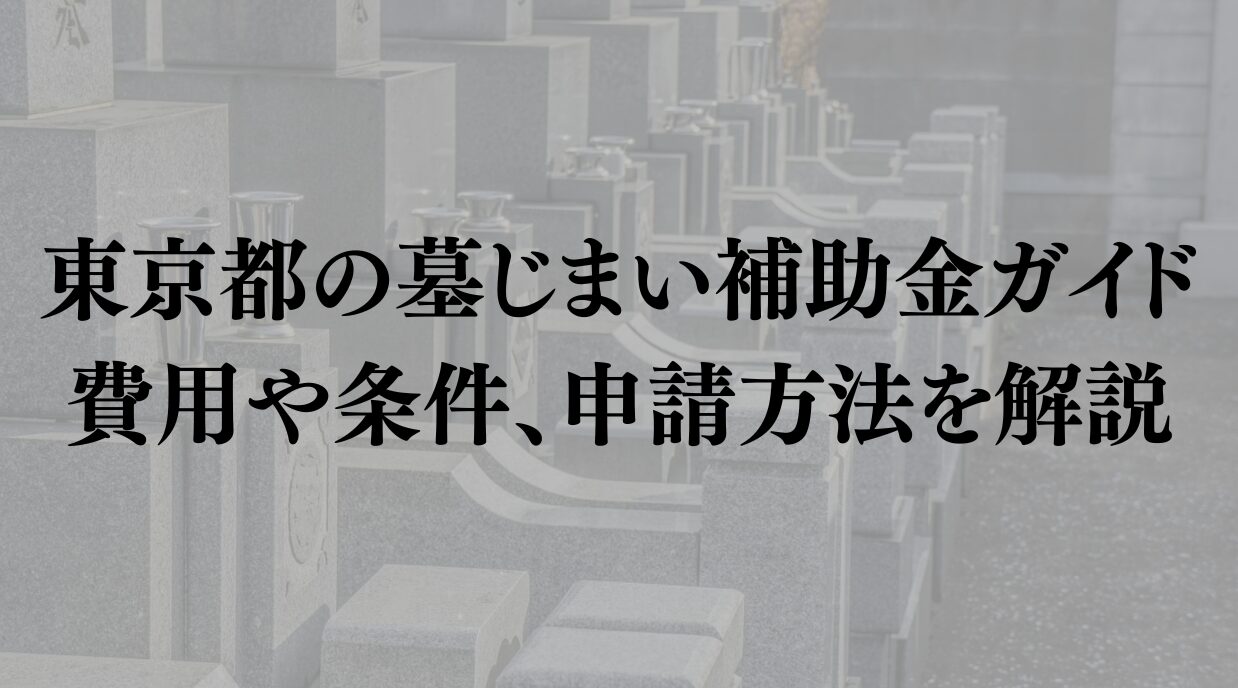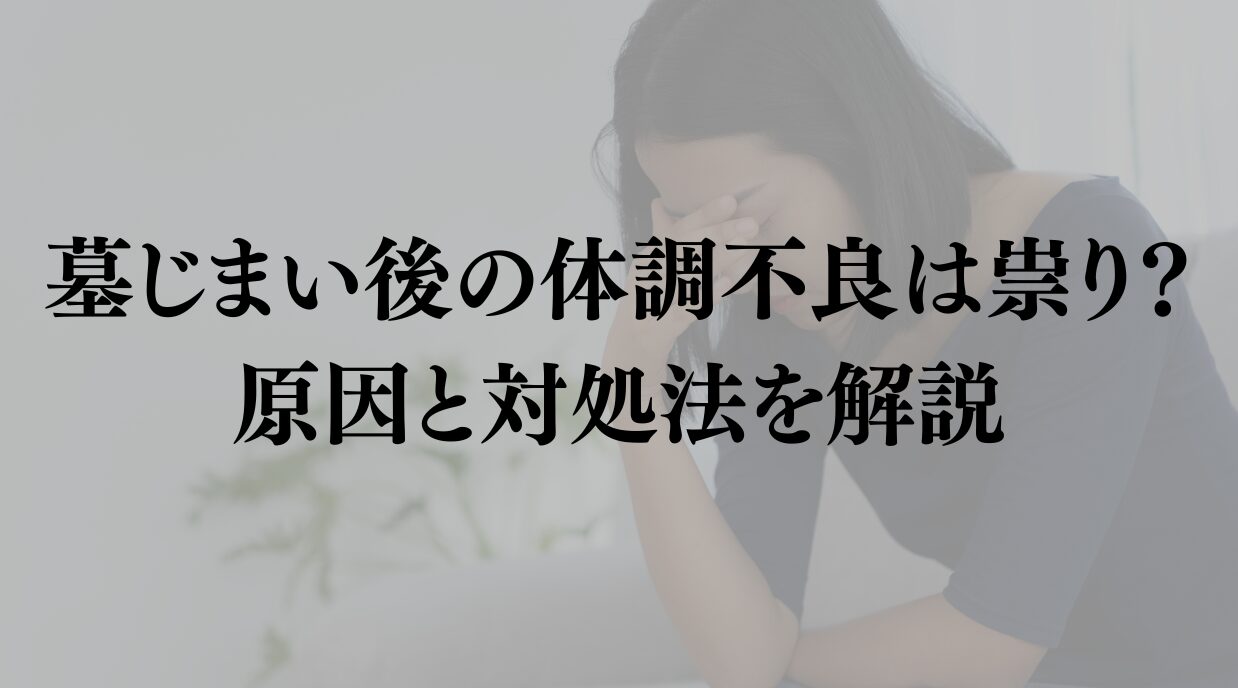真言宗の墓じまいを検討されているものの、一体どれくらいの費用がかかるのか、どのような手続きが必要なのか、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。墓じまいの費用の内訳や、真言宗ならではの閉眼供養のお布施、気になる離檀料の問題、そして煩雑な行政手続きまで、考えるべきことは多岐にわたります。
さらに、親族とのトラブルを避けつつ、墓石撤去や新しい永代供養先を探す必要もあり、どの石材店に相談すればよいのか悩むケースも少なくありません。この記事では、そのようなお悩みや疑問を解消するため、真言宗の墓じまいに関する費用や流れ、注意点を網羅的に解説します。
この記事を読むことで、以下の点について深く理解できます。
- 真言宗の墓じまいにかかる費用の総額と詳しい内訳
- 閉眼供養のお布施や離檀料などお寺との費用相場
- 行政手続きから墓石撤去までの具体的な流れと手順
- 費用を抑え円満に墓じまいを進めるためのポイント
墓じまい費用、真言宗の相場と内訳を解説
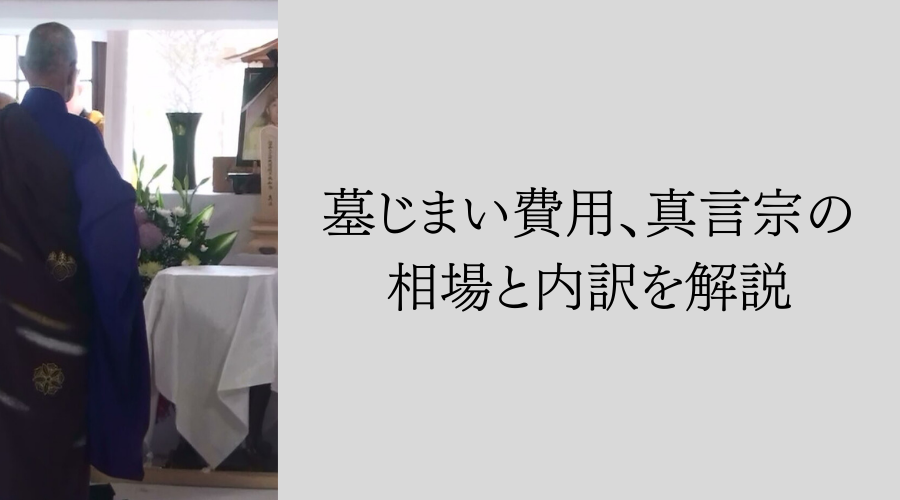
墓じまい全体の流れと期間の目安
墓じまいを始めると決めてから完了するまでには、一般的に3ヶ月から半年程度の期間が必要です。これは、関係者との話し合いや各種手続き、そして実際の工事などに相応の時間がかかるためです。急いで進めるとトラブルの原因にもなりかねないため、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切になります。
墓じまいの大まかな流れは、以下の通りです。
| ステップ | 内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 1. 親族間の合意形成 | 墓じまいを行うことについて、親族や関係者全員の同意を得ます。 | 1ヶ月〜 |
| 2. 墓地の管理者に連絡 | 現在のお墓があるお寺や霊園の管理者に、墓じまいの意向を伝えます。 | – |
| 3. 新しい納骨先の決定 | 遺骨を移す新しいお墓や納骨堂などを探し、契約します。 | 1ヶ月〜 |
| 4. 行政手続き | 自治体で「改葬許可証」を取得するための手続きを行います。 | 2週間〜1ヶ月 |
| 5. 閉眼供養 | お墓から魂を抜くための儀式「閉眼供養」を執り行います。 | – |
| 6. 遺骨の取り出し | 石材店にお墓を開けてもらい、遺骨を取り出します。 | 1日 |
| 7. 墓石の撤去・処分 | 墓石を解体・撤去し、更地に戻して管理者に返還します。 | 1日〜数日 |
| 8. 新しい納骨先への納骨 | 取り出した遺骨を、新しい納骨先へ納めます。 | – |
このように、墓じまいには多くの手順が存在します。特に親族間の話し合いや新しい納骨先探しには時間がかかる場合があるため、計画的に進めることが円満な墓じまいの鍵となります。
費用の内訳に影響する主な項目
墓じまいの費用は、お墓の状況や新しい納骨先の選択によって大きく変動し、総額で30万円から300万円程度が一般的な目安です。費用の内訳は、主に以下の4つに大別できます。
- お寺に支払う費用: 閉眼供養のお布施や、これまでお世話になった感謝を示す離檀料などが含まれます。
- 墓石の撤去・処分費用: 墓石を解体し、土地を更地に戻すための工事費用です。
- 新しい納骨先の費用: 永代供養墓や納骨堂、樹木葬など、新しい供養先に支払う費用を指します。
- 行政手続きの費用: 改葬許可申請に必要な書類の発行手数料などです。
墓じまい費用の相場一覧表
| 項目 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| お寺に支払う費用 | ||
| 閉眼供養のお布施 | 3万円 ~ 10万円 | 宗派や地域、お寺との関係性で変動 |
| 離檀料 | 3万円 ~ 20万円 | 法的義務はないが、感謝の気持ちとして渡すのが一般的 |
| 墓石の撤去・処分費用 | 10万円 ~ (1㎡あたり) | 墓地の立地や墓石の大きさで変動 |
| 新しい納骨先の費用 | ||
| 永代供養墓(合祀) | 5万円 ~ 30万円 | 他の方の遺骨と一緒に埋葬される |
| 永代供養墓(個別) | 30万円 ~ 150万円 | 一定期間は個別に安置される |
| 納骨堂 | 20万円 ~ 150万円 | ロッカー型、仏壇型など種類が豊富 |
| 樹木葬 | 20万円 ~ 80万円 | 墓石の代わりに樹木を墓標とする |
| 行政手続き費用 | 数百円 ~ 1,500円程度 | 各種証明書の発行手数料 |
| 合計 | 30万円 ~ 300万円程度 |
これらの費用はあくまで目安であり、個別の状況によって大きく異なります。特に墓石の撤去費用は、重機が入れない場所などでは高額になる傾向があるため、注意が必要です。
真言宗の閉眼供養のお布施相場
閉眼供養は、お墓に宿っている故人の魂を抜き、ただの石に戻すための大切な儀式です。これは宗派を問わず行われるもので、「魂抜き」や「お性根抜き」とも呼ばれます。真言宗においても、この閉眼供養を執り行ってから墓石の撤去工事に移るのが正式な手順です。
この際、僧侶にお渡しするお布施の相場は、3万円から10万円程度とされています。ただし、お布施はあくまで感謝の気持ちを表すものであり、明確な金額が決められているわけではありません。お寺との関係性の深さや地域性によっても変動するため、一概には言えないのが実情です。
もし金額に迷う場合は、事前にお寺へ「皆様おいくらくらいお包みされていますか」と率直に尋ねてみても失礼にはあたりません。また、お布施とは別に「御車代」として5千円から1万円程度、会食を設けない場合は「御膳料」として同じく5千円から1万円程度を包むのが丁寧な対応です。
離檀料は必ず支払う必要があるのか
離檀料とは、これまでお墓の管理でお世話になったお寺の檀家をやめる際に、感謝の気持ちとして支払うお金のことです。この離檀料に関して、法的な支払い義務は一切ありません。したがって、お寺から高額な離檀料を請求されたとしても、それに応じる必要はないのです。
しかし、これまで先祖代々お世話になってきたお寺への感謝の気持ちとして、3万円から20万円程度(法要1回分のお布施が目安)を包むのが一般的で、円満な墓じまいのために推奨されています。あくまで「お布施」や「御礼」という形で渡すのが良いでしょう。
一方で、残念ながら一部のお寺では、高額な離檀料を請求されるトラブルも報告されています。もし法外な金額を要求された場合は、まず他の寺院の住職や、墓じまいを専門とする行政書士、または弁護士に相談することをおすすめします。感情的にならず、冷静に対処することが解決への近道となります。
墓石の撤去と処分にかかる費用
墓じまいにおける物理的な作業の中心が、墓石の撤去と処分です。これは、お墓があった土地を更地に戻し、墓地の管理者に返還するために必要な工事を指します。費用は墓地の面積によって計算されるのが一般的で、1平方メートルあたり10万円から15万円程度が相場です。
ただし、この費用は様々な条件によって変動します。
- 墓地の立地: 山間部や道が狭い場所など、重機が入りにくい立地では人件費がかさみ、費用が高くなる傾向があります。
- 墓石の大きさや種類: 大きな墓石や特殊な構造を持つお墓は、解体や運搬に手間がかかるため、費用が上乗せされることがあります。
- 基礎工事の有無: 墓石の下に頑丈な基礎コンクリートが打たれている場合、その撤去にも追加の費用が発生します。
墓石の撤去は、専門の石材店に依頼するのが一般的です。後述しますが、複数の業者から見積もりを取り、作業内容と費用をしっかりと比較検討することが、費用を抑える上で非常に大切です。
新しい納骨先と永代供養の選択肢
墓じまいで取り出した遺骨を供養するための、新しい納骨先を確保する必要があります。近年では、お墓の承継者がいない家庭の増加に伴い、様々な永代供養の形が選ばれるようになりました。
永代供養とは、遺族に代わって霊園や寺院が遺骨を管理・供養してくれる方法です。主な選択肢として、以下のようなものがあります。
新しい納骨先の種類と費用相場
- 合祀墓(ごうしぼ): 費用相場は5万円~30万円程度。他の方の遺骨と一緒に、一つの大きなお墓や納骨施設に埋葬する方法です。費用を最も抑えられる一方で、一度納骨すると後から遺骨を取り出すことはできません。
- 集合墓: 費用相場は20万円~60万円程度。屋外に建てられた石碑やモニュメントの下に、個別の納骨スペースが設けられている形式です。
- 納骨堂: 費用相場は20万円~150万円程度。屋内に設けられた納骨スペースで遺骨を管理します。ロッカー型、仏壇型、自動搬送型など様々なタイプがあり、費用も大きく異なります。天候に左右されずお参りできるのが利点です。
- 樹木葬: 費用相場は20万円~80万円程度。墓石の代わりに樹木や草花をシンボルとして、その周辺に遺骨を埋葬する方法です。自然志向の方に人気があります。
- 一般墓: 費用相場は100万円~300万円程度。従来通り、新しく墓石を建てて供養する方法です。永代使用料や墓石工事費がかかるため、費用は高額になります。
どの供養方法を選ぶかによって、費用は大きく変わります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、故人の意向や家族のライフスタイルに合った選択をすることが求められます。
墓じまい費用を抑え真言宗で円満に進める方法

- 行政手続きと改葬許可証の申請手順
- 檀家としてお寺へ相談するタイミング
- 親族とのトラブルを避けるための準備
- 行政書士など専門家へ相談する利点
- 複数の石材店から見積もりを取る
- 補助金やローンは利用できるのか
行政手続きと改葬許可証の申請手順
墓じまいを行い、遺骨を別の場所に移すことを法律用語で「改葬(かいそう)」と呼びます。この改葬を行うためには、現在お墓がある市区町村の役所から「改葬許可証」を発行してもらう必要があります。この許可証がないと、遺骨を取り出したり、新しい納骨先に納めたりすることはできません。
手続きの基本的な流れは以下の通りです。
- 「改葬許可申請書」の入手: まず、現在のお墓がある市区町村の役所の窓口、またはウェブサイトから「改葬許可申請書」を入手します。
- 「埋葬証明」の依頼: 現在のお墓の管理者(お寺や霊園)に申請書を提示し、「このお墓に間違いなく遺骨が埋葬されています」という証明の署名・捺印をもらいます。
- 「受入証明書」の依頼: 新しい納骨先の管理者から、「遺骨の受け入れを承諾します」という証明となる「受入証明書」を発行してもらいます。
- 申請書の提出: 記入済みの「改葬許可申請書」「埋葬証明」「受入証明書」の3点を、役所に提出します。自治体によっては、これ以外の書類が必要になる場合もあります。
- 「改葬許可証」の交付: 書類に不備がなければ、役所から「改葬許可証」が交付されます。
これらの手続きには、数百円から1,500円程度の手数料がかかります。手続きは複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ着実に進めることが大切です。不明な点があれば、役所の担当窓口に相談しましょう。
檀家としてお寺へ相談するタイミング
長年お世話になってきたお寺の檀家をやめて墓じまいをする際は、お寺との関係を円満に保つことが非常に重要です。トラブルを避けるためには、相談するタイミングと伝え方に細心の注意を払う必要があります。
最も大切なのは、全ての事を決めてしまう前に、できるだけ早い段階でお寺に相談することです。 「墓じまいをすることに決めました」と事後報告するのではなく、「将来のお墓のことで相談がありまして…」という形で、まずは相談という形で話を切り出すのが良いでしょう。
相談のポイント
- 理由を正直に話す: 「お墓を継ぐ者がいない」「遠方に住んでいてお墓の管理が難しい」など、墓じまいを考え始めた理由を誠実に伝えます。
- 感謝の気持ちを伝える: これまで先祖代々お世話になったことへの感謝の気持ちを、言葉にしてしっかりと伝えることが大切です。
- 閉眼供養の相談: 墓じまいに際して、閉眼供養をお願いしたい旨を伝え、日程やお布施について相談します。
一方的な通知は、お寺側に不信感を与えかねません。これまでのお付き合いへの敬意と感謝を示す姿勢で臨むことで、お互いが気持ちよく墓じまいを進めることができます。
親族とのトラブルを避けるための準備
墓じまいは、費用面だけでなく、感情面でも親族間のトラブルに発展しやすい問題です。お墓は家族や親族にとって大切な場所であり、それぞれに故人への想いがあります。一人の判断で話を進めてしまうと、「なぜ相談してくれなかったのか」という不満から、深刻な対立につながる可能性があります。
このような事態を避けるために、必ず墓じまいを検討し始めた段階で、関係する親族全員に相談し、合意を得ることが不可欠です。
話し合いで明確にしておくべき点は以下の通りです。
- 墓じまいをする理由: なぜ墓じまいが必要なのか、その理由を丁寧に説明します。
- 費用分担: 総額でどれくらいの費用がかかるのかを提示し、誰がどのように分担するのかを具体的に話し合います。
- 新しい納骨先: どのような供養方法を考えているのか、候補となる場所や種類について情報を共有し、意見を聞きます。
- 今後の供養の方法: 墓じまい後の法要などをどうするのか、今後の関わり方についても話し合っておくと、後の誤解を防げます。
たとえ費用を一人で負担するつもりであっても、必ず全員の納得を得てから話を進めるようにしてください。丁寧なコミュニケーションが、円満な墓じまいのための最も重要な準備と言えます。
行政書士など専門家へ相談する利点
墓じまいに関する手続きは非常に煩雑で、時間も手間もかかります。また、お寺や親族との話し合いに精神的な負担を感じる方も少なくありません。そのような場合、行政書士などの専門家に相談・依頼するのも有効な選択肢の一つです。
専門家に依頼する主なメリットは以下の通りです。
- 煩雑な手続きの代行: 改葬許可申請など、時間のかかる行政手続きを全て代行してもらえます。
- お寺や石材店との交渉: 専門的な知識を基に、お寺や石材店との交渉を代行またはサポートしてくれます。離檀料に関するトラブルの際にも心強い存在です。
- 親族間の調整: 第三者の中立的な立場から、親族間の話し合いに入り、合意形成を円滑に進める手助けをしてくれます。
- 時間的・精神的負担の軽減: 慣れない手続きや交渉に費やす時間と精神的なストレスから解放され、本業や他のことに集中できます。
もちろん、専門家への依頼には5万円から20万円程度の費用がかかります。しかし、時間や労力、そしてトラブルのリスクを総合的に考えると、費用以上の価値があるケースも少なくありません。特に、遠方に住んでいる方や、話し合いに不安を感じる方は、一度相談を検討してみることをお勧めします。
複数の石材店から見積もりを取る
墓石の撤去・処分費用は、墓じまいの総費用の中でも大きな割合を占める項目であり、業者によって金額が大きく異なる場合があります。そのため、必ず複数の石材店から見積もり(相見積もり)を取ることが、費用を適正に保つ上で極めて重要です。
見積もりを依頼する際は、以下の点に注意してください。
- 最低でも3社以上から取る: 比較対象を増やすことで、その地域の費用相場を把握しやすくなります。
- 現地調査をしてもらう: 電話やメールだけでなく、必ず現地を見てもらった上で正確な見積もりを出してもらいましょう。
- 見積書の内容を詳しく確認する: 「工事一式」といった曖昧な表記ではなく、「墓石解体費」「運搬費」「処分費」など、内訳が詳細に記載されているかを確認します。追加料金が発生する可能性の有無についても、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
安さだけで業者を選ぶのは危険です。不法投棄などのトラブルに巻き込まれる可能性もゼロではありません。見積もり時の対応の丁寧さや、実績、許可の有無などを総合的に判断し、信頼できる石材店を選ぶようにしましょう。
補助金やローンは利用できるのか
「墓じまいに使える補助金はないだろうか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。結論から言うと、国が定めた墓じまい専用の補助金制度は、現在のところ存在しません。
ただし、一部の地方自治体では、管理されなくなった墓地(無縁仏)を減らす目的で、墓地を更地にして返還する際に費用の一部を助成する制度を設けている場合があります。例えば、「墓所返還奨励金」や「無縁墳墓地改葬補助」といった名称で実施されていることがあります。
これらの制度は全ての自治体にあるわけではなく、条件も様々です。まずは、現在お墓がある市区町村の役所のウェブサイトを確認したり、窓口に問い合わせてみたりすることをおすすめします。
また、墓じまいの費用を一括で支払うのが難しい場合は、「メモリアルローン」の利用も選択肢の一つです。これは、お葬式やお墓に関する費用に使える目的別ローンで、一部の銀行や信販会社が提供しています。通常のフリーローンよりも金利が低めに設定されていることが多いですが、利用には審査が必要です。計画的に利用を検討しましょう。
まとめ:墓じまい費用、真言宗の注意点
この記事で解説した、真言宗の墓じまいに関する重要なポイントを以下にまとめます。
- 真言宗の墓じまい費用総額は30万円から300万円程度が目安
- 費用の内訳は主にお寺への費用、墓石撤去費、新しい納骨先費、行政手続き費に分けられる
- 墓じまい完了までの期間は3ヶ月から半年程度を見込む
- 真言宗の閉眼供養のお布施相場は3万円から10万円が一般的
- 離檀料に法的な支払い義務はないが感謝の気持ちとして渡すのが円満の秘訣
- 高額な離檀料請求には専門家へ相談する
- 墓石の撤去費用は1㎡あたり約10万円からが相場だが立地条件で変動する
- 新しい納骨先は永代供養墓、納骨堂、樹木葬など選択肢が多様
- 遺骨を移動させるには役所で「改葬許可証」の取得が必須
- お寺には事後報告ではなく早い段階で相談することが大切
- 親族とは必ず事前に話し合い全員の合意を得る
- 費用分担や新しい供養方法についても親族間で明確にする
- 煩雑な手続きは行政書士への依頼も有効な選択肢
- 石材店は必ず複数の業者から見積もりを取って比較検討する
- 自治体によっては墓地返還に関する補助金制度がある場合も